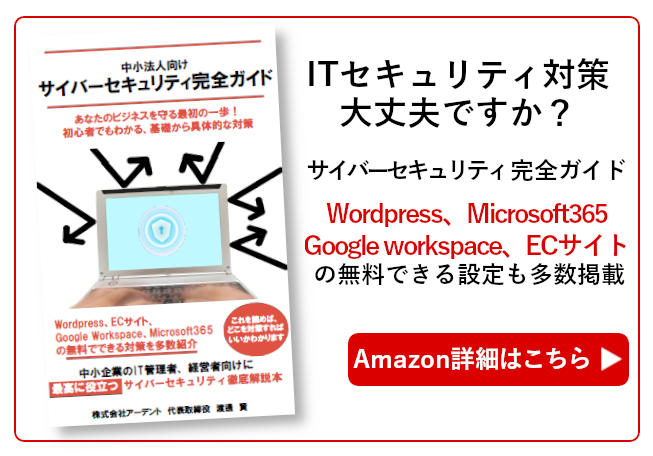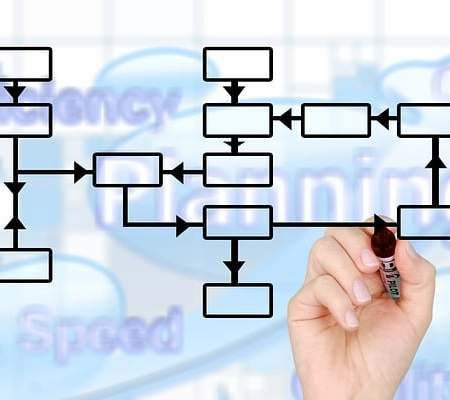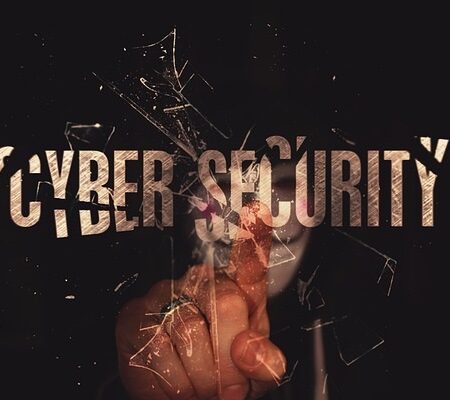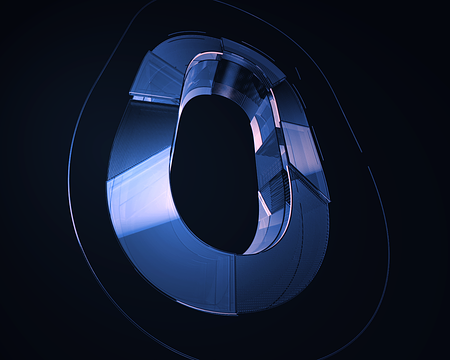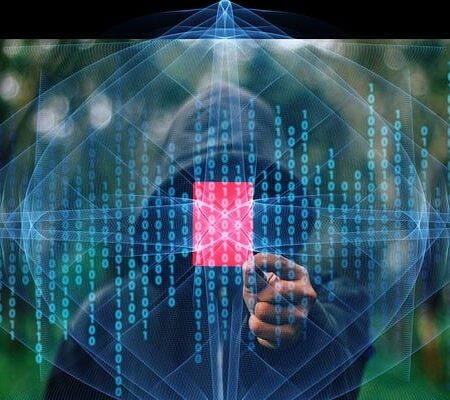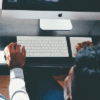情報漏えいが起きたらいくらかかる?損害賠償の現実

情報漏えいとは、個人や組織が保有する機密情報が外部に流出することを指します。情報漏えいが発生すると、企業は信用を失うだけでなく、場合によっては顧客や取引先から損害賠償を請求されるケースもあります。では、実際にどれくらいの金額を支払う可能性があるのでしょうか。
本記事では、情報漏洩による損害賠償の金額や相場などを解説します。国内の情報漏えいによる損害賠償の事例や、情報漏えいを防ぐ方法も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
損害賠償とは
そもそも損害賠償とは、不法行為や契約違反によって他人に損害を与えた場合、その損害を金銭で補償することを指します。損害賠償は大きく下記の2種類に分類できます。
①債務不履行による損害賠償:契約で定められた義務を果たさなかった場合に発生する損害賠償
②不法行為による損害賠償:故意または過失によって他人の権利や利益を侵害した場合に発生する損害賠償
情報漏洩は、②不法行為による損害賠償に該当します。
一般的な損害賠償額は被害者1人あたり数千円から数万円
情報漏えいによる損害賠償額は、被害者1人あたり数千円から数万円程度が一般的な相場とされています。
流出した情報が氏名や連絡先などの基本的な内容にとどまり、二次被害も発生していない場合、比較的軽度の被害とみなされて1人あたり3,000~5,000円程度に設定されるケースが多いです。
一方で、住所・金融情報・健康情報といったセンシティブなデータが漏洩したり、フィッシング詐欺や不正利用などの二次被害が発生したりした場合、被害が深刻と判断され、1人あたり30,000〜50,000円程度に金額が引き上げられるケースもあります。
国内の情報漏えいによる損害賠償の事例
続いて、国内の情報漏えいによる損害賠償の事例を3つ紹介します。
①【ベネッセコーポレーション】顧客情報流出で総額1100万円の賠償
2014年、ベネッセコーポレーションで顧客情報が大量に流出する事件が発生しました。流出データは委託先の従業員が不正に持ち出し、名簿業者に売却したものでした。
訴訟の結果、東京地裁は原告約5,000人のうち3,338人に対し、総額1,100万円の賠償を命じました。判決では、ベネッセが委託先のセキュリティ監査を十分に行っていなかった点が指摘されています。
②【Yahoo! BB】約450万人分の顧客情報を漏えい
2004年、Yahoo! BBで約450万人分の顧客情報が流出しました。流出データには氏名、住所、電話番号、携帯番号が含まれており、日本でも最大級の個人情報流出事件の一つとされています。
同社は発覚後、顧客へのお詫びとして500円分の金券を送付。また、アクセス権限の削減や従業員教育など、649項目におよぶセキュリティ対策を発表しました。
③【エステティックTBC】Webサイトから約3万件の顧客情報が流出
2002年、エステティックTBCのWebサイトで、約3万件の顧客情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・アンケート回答など)が流出しました。原因は委託先企業のサーバー移行作業ミスで、特定のURLにアクセスすれば誰でも閲覧できる状態になっていました。
2007年、東京地裁は TBCが使用者責任を負うべき と判断し、賠償金の支払いを命じました。
これらの事例から分かるのは、情報漏えいは金銭的な賠償責任だけでなく、 顧客対応・信用失墜・再発防止策のコストなど、企業に甚大な影響を与えるということです。情報漏えいを防ぐためにはどのような対策を講じるべきか、次章で詳しく解説します。
情報漏えいを防ぐ方法
情報漏洩を防ぐための方法は多くありますが、代表的な方法は下記の3つです。
●情報管理のルールを策定する
●社員に対してセキュリティ教育を実施する
●セキュリティツールを活用する
それぞれ解説していきます。
情報管理のルールを策定する
まずは、社内で情報管理のルールを策定し、社員に徹底させることが基本です。具体的には下記のような対策が挙げられます。
●情報の分類:顧客情報・機密情報・一般情報などにレベル分けし、取り扱い基準を設定する
●データの持ち出しを制限する:USBメモリや外付けHDDなどの使用を禁止、または暗号化を義務化する
●パスワードポリシー:複雑なパスワードの設定や定期的な変更を義務付ける
社員に対してセキュリティ教育を実施する
情報漏えいの多くは、人為的なミス(誤送信・誤操作・不注意) によって発生します。これを防ぐには、社員のセキュリティ意識を高める教育が不可欠です。
セキュリティ研修だけでなく、eラーニングや模擬の攻撃メール訓練(フィッシング詐欺を想定したテストメールを配信し、どれだけ社員が対応できるかを確認する)なども実施しましょう。日常的にセキュリティを意識できる仕組みを作ることで、人為的ミスによる情報漏えいを大幅に減らすことが可能です。
セキュリティツールを活用する
社内ルールやセキュリティ教育だけでは、人間のミスを完全に防ぐことはできません。そこで重要になるのが、技術的な対策=セキュリティツールの活用です。ツールを活用することで、情報漏えいのリスクをより軽減しやすくなります。情報漏えいを防止できる代表的なセキュリティツールは下記の3つです。
①アクセス制御ツール
多要素認証(MFA)やシングルサインオンを導入すれば、不正ログインやアカウントの乗っ取りを防止できます。社員が複数のシステムを利用する場合においても、安全かつ効率的にログインできる仕組みを実現することが可能です。
②DLP
DLP(Data Loss Prevention)を活用すれば、メールやクラウドサービスにアップロードされるデータを自動的に監視し、機密情報が含まれていないかをチェックできます。不適切な情報の送信や持ち出しを未然に防止できるのがメリットです。
③MDM
MDM(Mobile Device Management)は、業務で使用する端末を遠隔から一括管理できるツールです。万が一端末を紛失しても遠隔ロックやデータ消去などを実施できるため、情報漏えいのリスクを大幅に軽減できます。
まとめ
今回は、情報漏洩による損害賠償の金額や相場などを解説しました。
情報漏えいは一度発生すると、金銭的な損害だけでなく、企業の信用失墜や顧客離れといった深刻な影響をもたらします。被害者1人あたり数千円から数万円の賠償が必要になるケースもあり、被害規模が大きければ総額で数千万円〜数億円にのぼる可能性もあるでしょう。
情報漏えいのリスクを回避するためには、社内ルールの整備や社員教育、セキュリティツールの導入を組み合わせた多層的な対策が欠かせません。企業規模にかかわらず、早めに対策を講じるようにしましょう。
法人向けセキュリティソフトの
料金自動一括比較サイトを新しくオープンしました!
c-compe.com⇒
株式会社アーデントは、デジタル化・AI導入補助金の支援事業者を行っております!
アーデントからデジタル化・AI導入補助金を使ってクラウドツールを導入するメリットは以下の通りです。
メリット①対象ツールを2年間、半額、もしくは1/4で利用可!
メリット②会計、経費精算、請求書処理、受発注ツール導入なら、PCやタブレットの購入も補助が受けられ半額!
メリット③補助期間終了後は、公式価格よりお値引き!
メリット④各種IT活用、DX、保守サポートでより貴社のIT化を促進、生産性を向上します!
【弊社取り扱いクラウドツール】
🔹オフィスソフト・グループウェア: Google Workspace※、Microsoft365、desk'nets NEO※
🔹ノーコード業務改善:kintone、Zoho※、楽楽販売、JUST.DB※、サスケworks
🔹コミュニケーション: サイボウズオフィス、Chatwork、LINE WORKS、zoom
🔹会計・経費管理: マネーフォワード、freee、楽楽精算、楽楽明細、invox
🔹電子契約・文書管理: freeeサイン、クラウドサイン、GMOサイン、Adobe Acrobat
🔹セキュリティ対策: sophos、SentinelOne、ESET、ウイルスバスタークラウド
🔹RPA・自動化: RoboTANGO、DX-Suite、Yoom※、バクラクシリーズ
🔹勤怠・労務管理: 勤革時、楽楽勤怠、マネーフォワード
🔹物流・在庫管理: ロジザードZERO
🔹教育・マニュアル作成管理: iTutor、NotePM、leaf
🔹PBX・電話システム: INNOVERAPBX※、MOTTEL※
🔹端末管理:LANSCOPE、clomo
🔹リモートデスクトップ:RemoteOperator在宅
🔹受付ipad:ラクネコ※
🔹タスク管理、その他:JOSYS、backlog※
など
※こちらのツールは補助期間終了後の値引不可
また、上記以外のツールも取り扱いできるものが多々ありますので、一度ご相談ください。
デジタル化・AI導入補助金2026の詳細、お問合せはお電話頂くか、以下の記事を御覧ください↓
デジタル化・AI導入補助金お問合せ:03-5468-6097
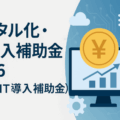
以下の動画では、採択のポイントや申請にあたっての注意点などを詳しく解説していますので、
あわせてご覧ください!